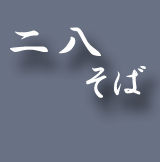江戸時代中期頃、江戸浅草芝崎町に、浄土宗の一心山極楽寺称往院という念仏道場があり、
その院内に道光庵という支院があった。
この庵主は信州の生まれだったので、蕎麦が好きだっただけでなく、蕎麦打ちも大変上手だった。
そこで享保(1716-36)の頃から檀家の人々に自ら打った蕎麦を出して喜ばれていた。
蕎麦は浅い椀に盛った真っ白い御膳蕎麦で、寺方なので魚類のだしは
使わない精進汁に辛味大根の絞り汁を添えて出した。町の二八蕎麦しか知らなかった檀家の人々は
その旨さに驚き感心し、その蕎麦を目当てに盛んに押しかけるようになる。
更には檀家以外の人々までがその評判を聞きつけ、信心にかこつけて食べに来るようになったという。
寛延(1748-51)頃になると、その評判はいよいよ高まり、安永6年(1777)刊の評判記
”富貴地座位”中巻(江戸名物)では、本職の蕎麦屋を押しのけて筆頭に上げられるほどであった。
この”そば切り寺”道光庵の名声にあやかろうと、当時の蕎麦屋の間では競って屋号に庵号をつけるのが流行した。
天明7年(1787)刊名店案内75日に紹介されている東向庵(鎌倉河岸竜閑橋)
、東翁庵(本所緑町)、紫紅庵.(目黒)、雪窓庵(茅場町)の四軒がその先駆けで、
文化(1804-18)の頃にはその流行は頂点に達した。今でも残る庵号には、
長寿庵、松月庵、大村庵、萬盛庵などがある。
しかし道光庵のそば切りは長くは続かなかった。繁盛のあまり寺なのか蕎麦屋なのかわからなくなり、
見かねた親寺称往院の再三の注意にもかかわらず内緒で蕎麦を振舞い続けたため、
天明6年(1786)、ついには蕎麦禁断の石碑が門前に立てられ、大繁盛のそば切りは三代にして
打ち切られた。
|